EC事業を推し進めるにあたり、発送作業や在庫管理、返品対応に追われる事業者も多いのではないでしょうか?
『EC物流代行』を活用することで、物流の効率化が図れるだけでなく、コスト削減や顧客満足度の向上にも繋がります。
この記事では、EC物流代行のおすすめ7選や、選び方、メリット・デメリット、よくある質問のご紹介をしていきますのでぜひ最後までご覧ください。
テルヰでは、EC物流専門の代行サービス『HIGH LOGI』を提供しています。高い品質の物流サービスを提供するだけでなく、各お客様のニーズに合った物流戦略を提案することが可能です。
もし『HIGH LOGI』について詳しく知りたい方や、無料見積・倉庫見学を行いたい方は下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。
『EC物流代行』を活用することで、物流の効率化が図れるだけでなく、コスト削減や顧客満足度の向上にも繋がります。
この記事では、EC物流代行のおすすめ7選や、選び方、メリット・デメリット、よくある質問のご紹介をしていきますのでぜひ最後までご覧ください。
本記事はこんな方におすすめ!
- 物流アウトソーシングを検討しているけど、どこを選べばいいか分からない人
- 具体的な物流アウトソーシングのメリットを知りたい人
テルヰでは、EC物流専門の代行サービス『HIGH LOGI』を提供しています。高い品質の物流サービスを提供するだけでなく、各お客様のニーズに合った物流戦略を提案することが可能です。
もし『HIGH LOGI』について詳しく知りたい方や、無料見積・倉庫見学を行いたい方は下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。
EC物流代行会社とは?

EC物流代行業者とは?
商品の入庫から保管、ピッキング、梱包、発送、さらには在庫管理、返品・交換対応、情報管理まで、多岐にわたる物流プロセスを一元的に引き受けます。
自社で物流業務を行う場合、倉庫の確保、人件費、資材費、システム導入費用など、多くのコストと手間が発生するでしょう。
特にEC事業が成長するにつれて、これらの負担は増大し、本業である商品企画やマーケティングに集中できないといった問題も生じがちです。
EC物流代行会社を利用することで、これらの課題を解決し、物流コストの最適化、業務効率の向上、そして顧客満足度の向上に繋げることができます。
3PLとフルフィルメント
3PL(Third Party Logistics)
3PLは『サードパーティ・ロジスティクス』の略で、企業が物流業務を外部の専門業者に包括的に委託する形態を指します。単に倉庫や配送を代行するだけでなく、物流戦略の立案、物流システムの構築、物流コストの最適化など、サプライチェーン全体のコンサルティングから実行までを担うのが特徴です。
3PL業者は、顧客企業の物流課題を深く理解し、その解決のために最適な物流プロセスを提案・実行することで、長期的なパートナーシップを築きます。物流コストの削減だけでなく、リードタイムの短縮や物流品質の向上といった、より戦略的なメリットを追求する際に選択されることが多いです。
3PLは『サードパーティ・ロジスティクス』の略で、企業が物流業務を外部の専門業者に包括的に委託する形態を指します。単に倉庫や配送を代行するだけでなく、物流戦略の立案、物流システムの構築、物流コストの最適化など、サプライチェーン全体のコンサルティングから実行までを担うのが特徴です。
3PL業者は、顧客企業の物流課題を深く理解し、その解決のために最適な物流プロセスを提案・実行することで、長期的なパートナーシップを築きます。物流コストの削減だけでなく、リードタイムの短縮や物流品質の向上といった、より戦略的なメリットを追求する際に選択されることが多いです。
フルフィルメント(Fulfillment)
フルフィルメントは、ECサイトにおける『顧客が商品を購入してから、実際に商品を受け取るまでの一連のプロセス』を指します。具体的には、受注処理、決済処理、ピッキング、梱包、発送、配送、顧客対応(問い合わせ、返品・交換)、代金回収など、ECサイト運営におけるバックエンド業務のほとんどすべてを含みます。
EC物流代行会社の中には、このフルフィルメント業務全体を代行するサービスを提供しているところが多く、『フルフィルメントサービス』と称されることもあります。顧客体験の向上に直結する部分であり、特にEC事業者が本業に専念するために非常に有効なサービスです。
フルフィルメントは、ECサイトにおける『顧客が商品を購入してから、実際に商品を受け取るまでの一連のプロセス』を指します。具体的には、受注処理、決済処理、ピッキング、梱包、発送、配送、顧客対応(問い合わせ、返品・交換)、代金回収など、ECサイト運営におけるバックエンド業務のほとんどすべてを含みます。
EC物流代行会社の中には、このフルフィルメント業務全体を代行するサービスを提供しているところが多く、『フルフィルメントサービス』と称されることもあります。顧客体験の向上に直結する部分であり、特にEC事業者が本業に専念するために非常に有効なサービスです。
簡単にまとめると、3PLはより戦略的・包括的な物流全体の最適化を目指し、フルフィルメントはEC特有の受注から配送、顧客対応までの一連の顧客体験に関わる業務を指します。
多くのEC物流代行会社は、フルフィルメントサービスを提供しており、その中で3PL的な要素(物流戦略の提案など)を兼ね備えている場合もあるのが特徴です。
相場料金
| 費用項目 | 業界平均費用 / 月 |
|---|---|
| 基本費用 - システム料 | 1~3万円 |
| 基本費用 - 事務手続き料 | 1~3万円 |
| 変動費用 - 保管費 | 1坪:4,500~7,000円 |
| 変動費用 - 入庫費 | 16~40円 / 個 |
| 変動費用 - 検品費 | 10~30円 / 個 |
| 変動費用 - 梱包費 | 150~400円 / 個 |
| 変動費用 - 配送費 | 500~1,000円 / 件 |
かかる費用として大きく分けて基本費用である『固定費』と『変動費』の2種があります。
基本費用については業者によっては無料としているところもありますが、その場合は変動費用が割高になっているケースが多いので、業者を比較する際はトータル費用で確認するようにしましょう。
具体的な目安金額として、小規模なEC事業者(月間数百件程度の出荷)であれば、月額数万円〜数十万円が目安となることが多いです。
中規模〜大規模(月間数千件以上の出荷)になると、月額数十万円〜数百万円以上かかることもあります。
都度見積を取得して、各業者の価格やサービス内容について比較することがおすすめです。
おすすめのEC物流代行会社7選!

おすすめのEC物流代行会社については下記の通りです。
- ✓テルヰ『HIGH LOGI』
- ✓エスプールロジスティクス
- ✓オープンロジ
- ✓富士ロジテックホールディングス
- ✓スクロール360
- ✓ウルロジ
- ✓日新ECパートナーズ
順を追って特徴やポイントを解説していきます。
テルヰ『HIGH LOGI』
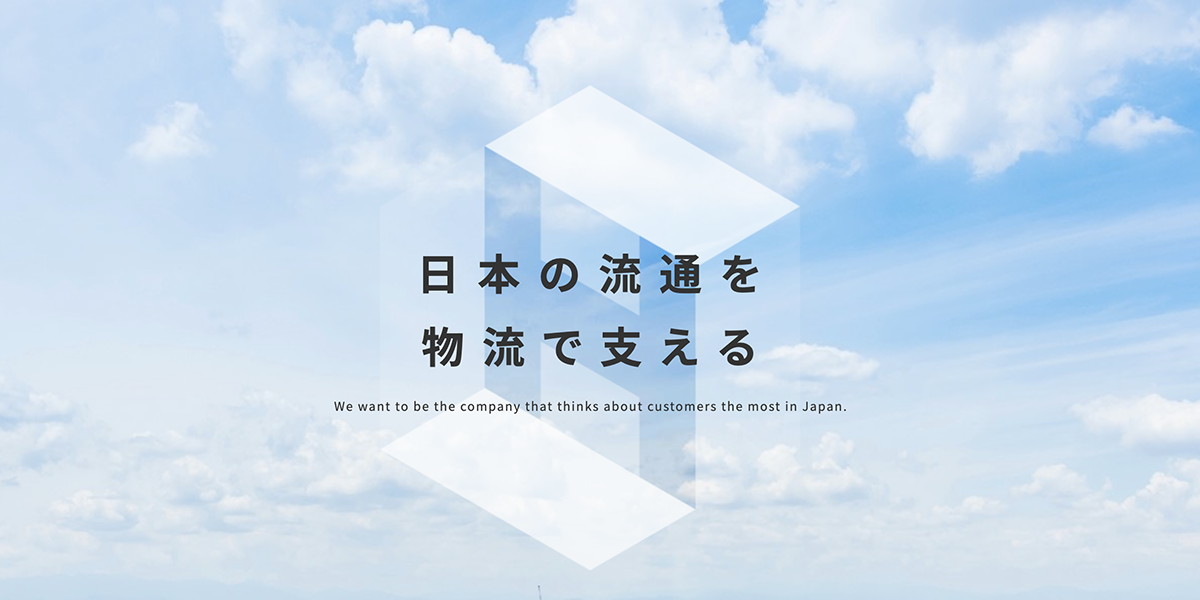
テルヰが提供する『HIGH LOGI』は、アパレル・化粧品・雑貨・サプリメント・加工食品などといった多様な商材に対応しているのが大きな特徴です。
また、当社の強みとしては、徹底した品質管理と、顧客に合わせた柔軟なカスタマイズ対応にあります。
複数の商材を扱っている企業や、個別の物流課題を抱えている企業に対して、物流効率化やルート最適化、コスト削減案など物流戦略を提案することが可能です。
ただの物流業者としてではなく、品質とコストのバランスを重視した信頼性の高い物流パートナーとして、お客様の事業成長をサポートいたします。
当社サービス内容について詳しく知りたい方、無料見積・倉庫見学をご希望の方はぜひ下記よりお問い合わせください。
エスプールロジスティクス

エスプールロジスティクスは、変動する物量に柔軟に対応できるシェアリング型のアウトソーシングサービスが強みです。
複数の荷主企業が共同で物流センターを利用する独自のビジネスモデルにより、効率的な運用を実現しています。
特に、キャンペーンや季節によって出荷量が大きく変動するEC事業者にとって、過剰な設備投資や人員確保のリスクを抑えながら、安定した物流体制を構築できる点が大きなメリットです。
同社は『圧倒的なコストパフォーマンスと高い汎用性』をアピールしており、荷主ごとに異なる自動化処理や同梱物制御ができるシステムを導入しているため、様々なECビジネスのニーズに対応可能です。
教育コストをかけずに経験豊富なスタッフによる作業分担ができる点も、物流担当者や経営者にとって魅力的なポイントです。
参考:エスプールロジスティクスホームページ
オープンロジ

オープンロジは、『初期費用・固定費ゼロ』から始められる従量課金制の料金体系が最大の魅力です。
月間の出荷件数が少ないスタートアップ企業や、まずは小規模から物流アウトソーシングを試してみたいEC事業者にとって、非常に導入しやすいサービスと言えます。
Webサイトからメールアドレスで会員登録するだけで即サービスを利用開始でき、スマートフォンやPCからオンライン上で業務指示を完結できる手軽さも特徴です。
全国の提携倉庫ネットワークを活用し、すべての提携倉庫に同一システムを導入しているため、倉庫の場所や規模による機能性の相違が少なく、スムーズな分散出荷もできます。
ShopifyなどのECプラットフォームとの連携も充実しており、在庫管理の一元化や作業の効率化にも貢献します。透明性の高い料金体系と導入の手軽さを重視するEC事業者におすすめです。
参考:オープンロジホームページ
富士ロジテックホールディングス

富士ロジテックホールディングスは、創業100年以上の歴史を持つ老舗の総合物流企業であり、その豊富な実績とノウハウが強みです。
関東、中部、関西、福岡に自社物流センターを構え、アパレルや化粧品、冷凍・冷蔵食品、大型商品など、多岐にわたる商材のEC物流代行に対応しています。
B2Cだけでなく、B2B物流も一括で請け負うことが可能であり、オムニチャネル物流を構築したい企業にも適しているでしょう。
多くのeコマース販売チャネルやマーケットプレイス、コマースシステムとAPI連携が可能であり、出荷の自動化と効率化も実現できます。
安定した高品質な物流サービスと包括的なサポートを求めるEC事業者におすすめです。
参考:富士ロジテックホールディングスホームページ
スクロール360

スクロール360は、大手通販企業スクロールのグループ会社が運営するEC物流代行サービスであり、通販事業で培った60年以上の実績とノウハウが最大の強みです。
EC・通販事業者様の利益最大化をミッションに掲げ、物流業務だけでなく、顧客対応や決済代行、システム連携など、通販業務全般を『まるごと360度』トータルでサポートできる点が魅力となります。
特に、商品を受け取る顧客の体験を重視した『まごころフルフィルメント』を提唱しており、単なるコスト削減に留まらない、顧客満足度向上に貢献する質の高いサービスを提供していることも強みと言えるでしょう。
通販プロフェッショナル集団による戦略的な次世代CRM物流を目指しており、複雑なバックオフィス業務もまとめてアウトソーシングしたいEC事業者にとって、信頼できるパートナーです。
参考:スクロール360ホームページ
ウルロジ
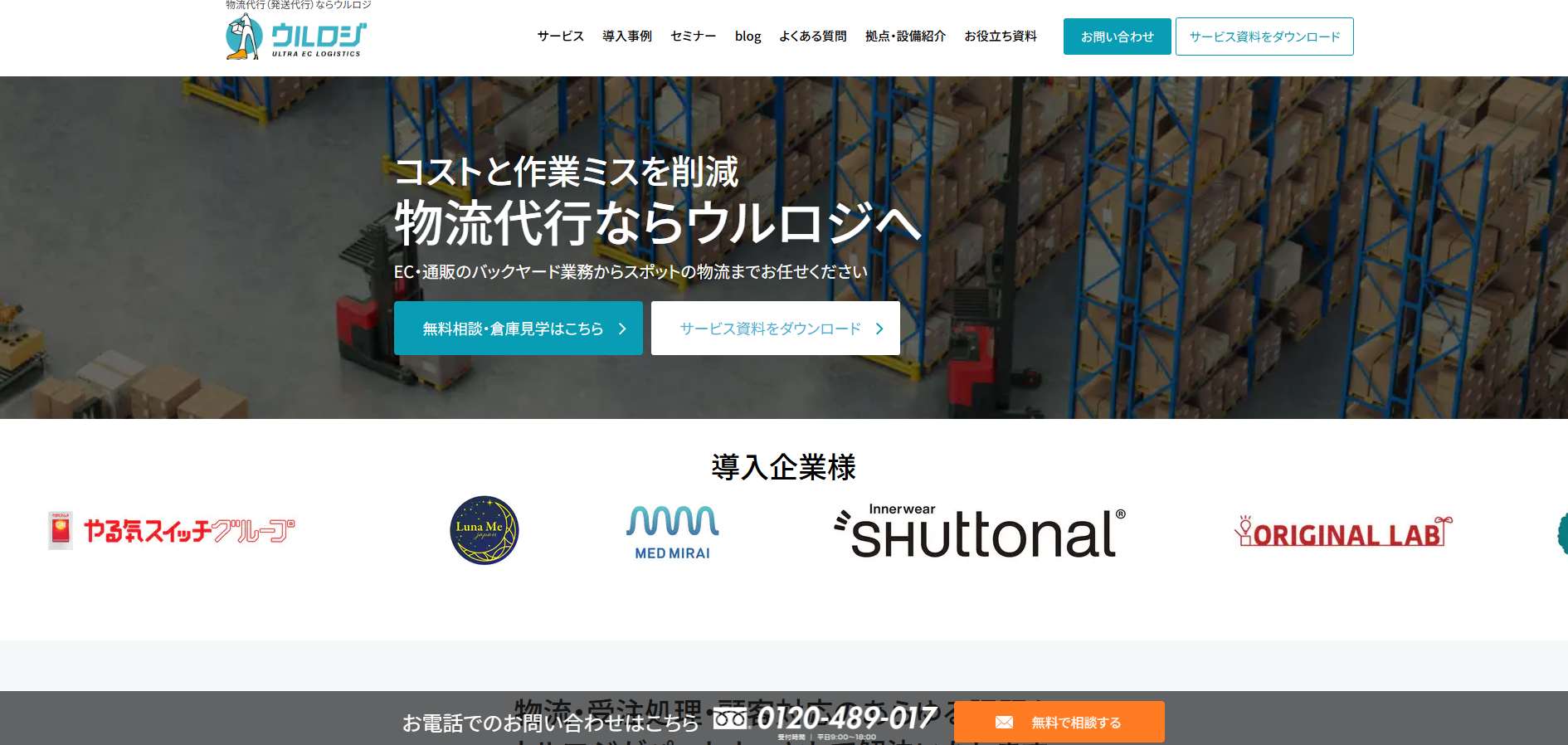
ウルロジは、中小規模のEC事業者に特化したきめ細やかなサービスと明朗会計が特徴のEC物流代行会社です。
特に『圧倒的に少ない発送ミス』を強みとしており、大規模な設備投資によって実現された高い品質管理が評価されています。
都内に4拠点の自社倉庫を保有し、13時までのご注文で当日出荷が可能、さらに365日対応も開始しており、スピーディーな配送が実現可能です。
月1個からの小ロット発送や、顧客満足度向上のための細やかなカスタマイズにも柔軟に対応してくれるため、初めて物流アウトソーシングを検討する事業者や、個別の要望が多い企業でも安心して利用できます。
梱包資材費込みで全国一律料金のシンプルな料金体系も魅力の一つです。
参考:ウルロジホームページ
日新ECパートナーズ

日新ECパートナーズは、総合物流企業である日新グループが提供するEC物流サービスです。
『ワンパッケージで安い』料金体系が特徴で、倉庫利用費込みで出荷1件あたり550円から対応可能(内容により変動あり)と、非常に分かりやすい料金設定を提示しています。
初期費用・固定費0円で、1件からの小ロット出荷にも対応しているため、物流の出荷件数がまだ少ない企業でも導入しやすいでしょう。
申し込みから1日で利用開始でき、Webで全ての運用・操作が完結するため、スピーディーな導入と効率的な管理が可能です。
また、独自のEC専用物流システム『mylogi』を構築し、自動出荷やワークフローの徹底により、0.5PPM(200万件に1件以下)という業界トップクラスの誤出荷率を実現しています。
越境ECにも対応しており、将来的な海外展開を見据えているEC事業者にも頼れるパートナーです。
参考:日新ECパートナーズホームページ
EC物流代行会社の選び方

様々なEC物流代行会社が多く、どこを選べばいいか分からないといった人も多いでしょう。自社にとって最適なパートナーを選ぶ方法として5つのポイントを挙げましたのでぜひご確認ください。
- ✓実績と信頼性
- ✓IT物流システムの活用
- ✓サービスの対応範囲
- ✓費用体系の透明性
- ✓現地への見学
実績と信頼性
これは、単に企業の歴史が長いかどうかだけでなく、どのような業種・商材の取り扱い実績があるか、過去にどのような課題を解決してきたか、といった点に注目することが重要となります。
同業種・同商材の実績については、あなたのEC事業と同じ、あるいは類似した商材(アパレル、食品、化粧品、精密機器など)の取り扱い経験が豊富であるかを確認しましょう。
特定の商材には、温度管理、薬機法対応、賞味期限管理、特殊な梱包など、専門的な知識や設備が必要となる場合があります。
実績がある会社は、これらの専門知識やノウハウを持っている可能性が高く、スムーズな導入と高品質なサービスが期待できるでしょう。
顧客からの評価や評判については、導入事例やお客様の声が公式サイトに掲載されているか、あるいは、実際に利用している他社の評判をリサーチするのも有効です。
良い口コミが多い会社は、それだけ顧客満足度が高い証拠と言えます。
危機管理体制については、災害発生時やシステムトラブル時など、不測の事態にどのように対応するのか、BCP(事業継続計画)が策定されているかなども、信頼性を測る上で重要なポイントです。
実績と信頼性のあるパートナーを選ぶことで、安心して物流業務を任せることができ、結果的に自社のEC事業の成長に集中できるようになります。
IT物流システムの活用
WMS(倉庫管理システム)やOMS(受注管理システム)など、どのようなシステムを導入しているかや、そのシステムが自社のECサイトや販売チャネルとスムーズに連携できるかは、選定の重要なカギとなります。
在庫数が常に正確に把握できるWMSやOMSは、欠品による販売機会損失を防ぎ、過剰在庫のリスクを低減できるでしょう。
また、リアルタイムで在庫状況を確認できることで、販売戦略を柔軟に立てることが可能です。
加えて、利用しているShopify、楽天、AmazonなどのECプラットフォームやカートシステムと、代行会社のシステムがAPI連携などによってスムーズに連動できるかも確認しましょう。
これにより、受注データの自動連携や出荷通知の自動送信が可能になり、手作業によるミスを減らし、業務効率を大幅に向上させることができます。
顧客への配送状況をリアルタイムで追跡できる機能があるかどうかも重要です。顧客からの問い合わせ対応にも役立ち、顧客満足度向上に繋がります。
さらに、出荷データや在庫データなどを分析し、物流コストの最適化や業務改善に繋がるレポートを提供してくれるシステムであれば、より戦略的な物流運営が可能です。
IT物流システムについて詳しく知りたい方は下記でも解説しておりますのでこちらもぜひご覧ください。
サービスの対応範囲
入庫・保管・ピッキング・梱包・出荷などの基本サービスは、EC物流代行の根幹をなすサービスですが、それぞれの工程においてどこまで細かく対応してくれるかを確認することが大切です。
流通加工に関しては、ギフトラッピング、熨斗掛け、セット組み、ネーム刺繍、タグ付け、検針など、商品に付加価値を加える流通加工に対応しているか確認しましょう。顧客体験に大きく関わる部分となります。
顧客からの返品・交換対応を代行してくれるかどうかも重要なポイントです。この業務は意外と手間がかかるため、任せられると業務負担が大きく軽減されます。
また、配送状況、返品・交換などの物流に関する顧客からの問い合わせを代行してくれるサービスもあります。自社での顧客対応リソースが不足している場合に有効でしょう。
なお、将来的に海外展開を考えている場合や、B2BとB2Cの両方をまとめて委託したい場合は、それらの対応可否も確認が必要です。
必要なサービスが網羅されているか、そして将来的な事業拡大にも対応できる柔軟性があるかを確認することで、長期的なパートナーシップを築ける会社を選べます。
費用体系の透明性
物流コストはEC事業の利益に直結するため、費用体系の透明性は非常に重要です。
見積もりの段階で、どのような項目に、どのような計算方法で費用が発生するのかを明確に提示してくれるかを確認しましょう。
初期費用、月額固定費、保管料、入庫、ピッキング、梱包、出荷などの作業料、送料、その他オプション費用など、全ての料金項目が明確に提示されているか確認することが重要です。
料金算出基準について、保管料が坪単価、容積単価、個数単価のどれなのか、作業料が件数単価、点数単価など、どの基準で算出されるのかを理解することが重要となります。
自社の商材特性や出荷量に合った料金体系であるかを見極めましょう。
また、概算ではなく、自社の出荷量や商品数、倉庫利用状況などを基にした具体的な見積を複数社から取得し、比較検討することをおすすめします。
物流代行業者が想定していなかった事項が複数出てくると、さらなる料金がかかり、想定よりはるかに高くなってしまった事例もあるので注意が必要です。
なお、契約内容については、契約期間、解約条件、料金改定の可能性など、契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消しておきましょう。
費用体系が明確で透明性の高い会社を選ぶことで、予期せぬコスト発生を防ぎ、安心して予算計画を立てることができます。
現地への見学
可能であれば、実際に物流センターや倉庫の現地見学をさせてもらうことをおすすめします。ウェブサイトや資料だけでは分からない、実際の現場の雰囲気や作業品質を肌で感じられるでしょう。
見学する上で重要なポイントは下記となります。
物流倉庫見学の10個の重要なチェックポイント!
- 倉庫外環境
- 倉庫内環境
- 対応できる商品
- 倉庫のレイアウト
- 入荷から出荷までの作業工程
- 倉庫の自動化
- 従業員の教育
- 安全管理
- セキュリティ対策
- 他社にはない強み
倉庫の内外環境、レイアウトやセキュリティなどについて確認することが重要です。また、入荷から出荷までどのように作業されているかを確認することで、サービスレベルの把握もできるでしょう。
当社であれば、倉庫見学については常時受け付けております。下記リンクよりお気軽にお申込みできるので、ぜひお気軽にご連絡ください。
なお、上記に挙げている物流倉庫見学の10個の重要なポイントについては下記の記事にて詳しく解説しております。詳細内容について気になる方はぜひこちらもチェックしてみてください。
物流代行の3つのメリット

物流代行を活用する大きなメリットは下記の3つです。
- ✓業務効率の向上と本業への集中
- ✓物流コストの最適化
- ✓物流品質の向上
順を追って解説していきます。
業務効率の向上と本業への集中
これらの業務を自社で行う場合、単に人手を割くだけでなく、作業スペースの確保、専用設備の導入、さらにはスタッフの教育や勤怠管理といった、多くの手間とコストが発生します。
特に、注文が急増するセール期間や特定のシーズンには、社内リソースだけでは対応しきれなくなり、残業代の増加や出荷遅延、さらには誤出荷といったトラブルに繋がりかねません。
これらの物流業務に追われることで、EC事業者が本来注力すべき商品企画、マーケティング戦略の立案、顧客対応といったコア業務への集中が難しくなるのが現状です。
しかし、物流代行サービスを利用することで、これらの煩雑な業務を専門業者に一任できます。
物流代行業者は、物流に特化したプロフェッショナル集団であり、効率的な倉庫運用体制、熟練のスタッフ、そして最新の物流システムを既に構築しています。
そのため、EC事業者は物流に関する時間や労力を大幅に削減し、商品開発、販売戦略の立案、顧客とのコミュニケーション強化といった、売上アップに直結する活動に集中することが可能になります。
結果として、事業全体の生産性向上と成長を加速させ、ECサイトの顧客体験価値を向上させることに繋がるでしょう。
物流コストの最適化
さらに、物量に変動があるEC事業の場合、閑散期には倉庫スペースや人員が過剰になりコストが無駄になったり、逆に繁忙期にはリソースが不足して機会損失に繋がったりと、常にコストを最適化することは難しいでしょう。
特に、商品が破損したり、顧客に届かなかった場合の再送費用なども考慮に入れると、見えないコストも膨らみがちです。
物流代行サービスは、これらのコストを変動費化できる点が大きなメリットとなります。
物流代行業者は複数のEC事業者から物流業務を受託することで、広大な倉庫スペースや多数の人材、効率的な運送網などを効率的に共同利用することが可能です。
この『スケールメリット』により、個々のEC事業者が自社で行うよりも、一つあたりの物流コストを大幅に抑えることができます。
また、物量の増減に応じて柔軟にサービスを調整できるため、ピーク時には人員を増強し、閑散期にはコストを削減するなど、無駄なコストを徹底的に排除し、物流コストの最適化を図ることが可能です。
これにより、EC事業者は固定費に縛られることなく、事業規模に応じた最適なコストで物流サービスを利用できます。
物流品質の向上
購入した商品がなかなか届かない、梱包が不十分で商品が破損していた、あるいは誤った商品が届いたなどのトラブルは、顧客にとって大きな不満となり、リピート購入の機会を失う大きな要因となります。
しかし、これらの高品質な物流対応をすべて自社で実現するのは容易ではありません。
特に、取り扱い商品が多岐にわたるECサイトや、複数の販売チャネルを展開する事業者にとっては、在庫管理の複雑化や物流品質の維持が大きな課題になります。
そこで重要視されているのが、『物流代行(EC物流アウトソーシング)』の活用です。
物流代行業者は、長年の経験とノウハウをもとに、効率的な倉庫管理システム(WMS)、熟練のピッキング・梱包技術、高精度な配送ネットワークを備えたプロフェッショナル集団と呼ばれています。
例えば、バーコードを活用した在庫・出荷管理による誤配送の防止、地域ごとの配送状況を加味した最適ルートの選定など、物流の各工程において高い精度と安定性を実現させられることが強みの一つです。
これにより、配送品質の向上とトラブルリスクの低減が可能となり、ECサイトの信頼性向上にもつながります。
さらに、多くの物流代行業者は、リアルタイムの在庫可視化や配送状況の追跡機能、さらには顧客からの問い合わせ対応まで一貫して対応可能なトータル物流ソリューションを提供していることも特徴です。
これにより、事業者は本来注力すべき販売・マーケティングに集中できるだけでなく、顧客へのサービス品質を強化することができます。
結果として、顧客満足度の向上やリピーターの増加につながり、ECブランドの信頼性と競争力の強化にも寄与するでしょう。
物流代行の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で物流代行を利用するデメリットも少なからず存在します。
デメリットについては下記の通りです。
- ✓場合によっては割高になることも
- ✓自社でコントロールしにくくなる
- ✓トラブル発生時の責任が不透明になりやすい
こちらも順を追って解説していきます。
場合によっては割高になることも
例えば、1日に数件しか発送のない小規模なECショップが、月額固定費+出荷単価制の代行業者と契約した場合、1件あたりの発送コストが自社出荷よりも高くなることがあります。
また、ギフトラッピングや緩衝材の指定など、ブランド独自の梱包仕様がある場合は追加費用がかかるケースもあるでしょう。繁忙期は従量課金が増え、コスト予測が立てづらいという声もあります。
ポイントとしては、 コスト面では『最低出荷数』や『固定費・変動費の内訳』『追加サービスの価格表』を事前に確認することです。
また、出荷量が増えた場合のシミュレーション見積も取得しておくといいでしょう。
自社でコントロールしにくくなる
例えば、『今この商品の在庫は本当にあるのか?』『急ぎ出荷したい注文があるが、伝達が届いているか?』といったタイミングでの確認がワンテンポ遅れがちです。
特に、季節商品やプロモーション連動の商品を販売している事業者では、出荷タイミングの微調整や臨機応変な対応が不可欠ですが、代行会社がマニュアルに従った運用を優先することで、柔軟性が失われる可能性があります。
『SNSでバズった商品を即日出荷したい!』という状況で、倉庫との連携がうまく取れず、タイミングを逃したというケースも少なくありません。
対策としては、 API連携やチャットツールでリアルタイムに情報共有できる体制を構築すると安心です。また、定期的にミーティングを実施し、常に最新情報を共有することも重要となります。
トラブル発生時の責任が不透明になりやすい
例えば、商品の破損が配送時なのか、倉庫での保管中なのかが曖昧なままだと、代行業者・配送業者・EC事業者の三者間で責任の押し付け合いが発生することもあるでしょう。
実際のトラブル例を挙げます。
トラブル例
- 梱包が甘く商品が破損 → 代行業者は『指示通り梱包した』と主張
- 納期遅延 → 倉庫の出荷ミスか配送会社の問題か不明
- 顧客クレームの原因調査に時間がかかり、対応が遅れる
こうしたトラブルが顧客体験を損ね、リピート率の低下やレビューの悪化につながる可能性もあります。
対策として、 契約書には『どこからどこまでが誰の責任かの責任分界点』を明記し、トラブル対応フローも定めておくと安心です。
よくあるQ&A|物流代行サービスの疑問を解消!

Q1. 大手と中小の違いは何ですか?
独自のWMS(倉庫管理システム)や配送ネットワークを有しており、大量出荷・短納期・スケーラビリティを求める企業に適しており、繁忙期にも安定したリソースを確保しやすいのが特徴です。
一方で、中小の物流代行業者は柔軟な対応やきめ細かなサービスが強みです。
例えば、商品の梱包方法のカスタマイズや、チャットツールを使ったスピーディーな連絡対応など、密なコミュニケーションができます。
スタートアップやD2Cブランドなど、自社らしさを重視するEC事業者に向いているでしょう。
Q2. 自社物流と物流代行の違いは何ですか?
業務を自社でコントロールできる反面、人件費や設備投資、管理工数がかかり、成長に伴って負担が大きくなりがちです。
一方、物流代行は、入荷から保管、ピッキング、梱包、出荷までを外部に委託する仕組みとなります。物量が増えても人員確保や作業スペースの問題が起こりにくく、スムーズにスケールアップ可能です。
ただし、業者との連携が不十分だとトラブルの原因になりやすいため、信頼できるパートナー選びが鍵となるでしょう。
Q3. 商品の在庫状況はリアルタイムで確認できますか?
SKUごとの在庫数、入出庫履歴、賞味期限管理(食品・化粧品の場合)など、詳細なデータが把握できるため、販売計画や在庫補充の判断にも役立ちます。
ただし、リアルタイム反映の頻度や表示項目は業者によって異なるため、事前に『どこまで見えるのか』『更新タイミングはどのくらいか』を確認するのがおすすめです。
Q4. 繁忙期(セール・年末など)も対応可能ですか?
あらかじめ繁忙期の出荷予測を伝えておくことで、追加人員の確保や作業スケジュールの調整を行ってくれるため、一定のリードタイムを設けておくことが重要です。
一部の業者では、事前申し込みがないと出荷制限がかかることもあるため、『繁忙期対応の柔軟性』『追加料金の有無』『処理能力の限界値』などを契約前に確認しましょう。
まとめ

EC物流代行のおすすめ7選や、選び方、メリット・デメリット、よくある質問のご紹介してきました。重要なことは、自社のニーズやスケールに合ったパートナー選びを行うことです。
サービスが魅力的でも、自社が求めるものに合わないのであれば意味がありません。
自社のニーズをしっかりと明確にし、スケール感の合った企業を選ぶことで、より効果的な物流を実現でき、顧客体験を最大限まで魅力的なものにできるでしょう。
当社は『日本で一番お客様のことを考える会社』を目指しており、どのようなニーズでも柔軟に対応できることが強みです。
もし、当社サービスについて気になることがあったり、無料見積を取得したい場合はぜひ、下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。
関連記事
・物流アウトソーシングの選び方は?メリットや成功事例について徹底解説
・FBA納品・梱包を効率化する方法は?失敗しない物流代行の始め方
・物流DXの成功事例7選と導入の5ステップ|物流の未来を切り拓く実践ガイド












