物流DXを行い劇的な物流最適化を行いたい方も多いのではないでしょうか?
物流DXを推し進めることで、労働生産性向上、コスト削減、顧客満足度向上など、様々なメリットを期待できます。
この記事では、物流DX導入のメリットと効果、7個の成功事例、導入するための5ステップについて解説いたしますのでぜひ最後までご覧ください。
テルヰでは、EC物流特化型の物流代行サービス『HIGH LOGI(ハイロジ)』を提供しており、在庫管理改善や、コスト削減など、物流DXのサポートを行っております。
無料のお見積やお問い合わせ、倉庫見学については下記よりぜひお気軽にお問い合わせください。
物流DXを推し進めることで、労働生産性向上、コスト削減、顧客満足度向上など、様々なメリットを期待できます。
この記事では、物流DX導入のメリットと効果、7個の成功事例、導入するための5ステップについて解説いたしますのでぜひ最後までご覧ください。
本記事はこんな方におすすめ!
- 物流DXの事例を参考にして物流DXを推し進めたい人
- 物流DXを推し進める上で具体的を知りたい人
テルヰでは、EC物流特化型の物流代行サービス『HIGH LOGI(ハイロジ)』を提供しており、在庫管理改善や、コスト削減など、物流DXのサポートを行っております。
無料のお見積やお問い合わせ、倉庫見学については下記よりぜひお気軽にお問い合わせください。
物流DXとは?

物流DXとは?
- 物流DXで活用される主な技術
- ✓WMS(倉庫管理システム)による在庫管理の最適化
- ✓TMS(輸配送管理システム)によるルートの自動最適化
- ✓IoTやセンサーでのリアルタイムデータ収集
- ✓AI・ビッグデータ分析による需要予測・業務改善
単なるシステム導入にとどまらず、データドリブンな意思決定によって全体最適を図るのが物流DXの特徴です。効率的かつ柔軟な物流体制を構築するため、多くの企業が導入を進めています。
物流DXの効果と導入メリット
- 主な導入効果
- ✓作業の自動化・標準化によりヒューマンエラーを削減
- ✓リアルタイム在庫管理で欠品・過剰在庫を防止
- ✓配送ルートの最適化により燃料費・配送時間を削減
- ✓データ可視化で経営判断が迅速に
また、業務が属人化している現場でも、DX導入によって誰でも運用できる仕組みが整い、安定したオペレーションが可能となります。
物流DXは、企業の競争力を高める戦略的施策として注目されており、物流アウトソーシングと組み合わせることで、さらに高い効果を発揮します。
上場企業の物流DX化!成功事例 3選

上場している大手企業のDX化の成功事例について3つ紹介いたします。
- ✓AI×ロボティクスでグローバル物流を最適化 | ユニクロ
- ✓ラストワンマイルまで可視化するEC物流DX | アスクル
- ✓外部倉庫とAPI連携で出荷の自動化・効率化 | メルカリ
AI×ロボティクスでグローバル物流を最適化 | ユニクロ
そこで同社は、AIとロボティクスを活用した次世代型の物流センターを構築しました。出荷、検品、梱包といった一連の作業を自動化し、作業負荷を軽減しました。
また、AIによる需要予測システムを導入し、在庫調整の精度向上も実現しています。
この結果、作業効率が大幅に向上し、リードタイムも短縮。人的ミスの削減とコスト削減に成功し、変化の激しいグローバル市場にも柔軟に対応できる体制を整備しました。
ユニクロの事例は、ロボットとAIの融合による物流DXの先進モデルといえるでしょう。
自動化やロボティクスについてさらに詳しく知りたい方は下記でも解説しておりますので、ぜひこちらもご覧ください。
ラストワンマイルまで可視化するEC物流DX | アスクル
アスクルは、物流DXの一環として配送状況のリアルタイム可視化と、配送ルートの最適化に着手。WMSやTMSを導入し、出荷から配送完了までの情報を一元管理するようにしました。
さらにAIを活用し、ドライバーの走行ルートも自動で最適化し物流最適化を実現しています。
これにより、再配達率の低減や即日配送の対応強化が実現し、顧客満足度が向上し、配送コストの削減にもつながる持続可能なEC物流体制を確立しました。
アスクルは、ラストワンマイルの課題解決に成功した代表的なEC物流DX事例です。
外部倉庫とAPI連携で出荷の自動化・効率化 | メルカリ
そこで同社は、外部フルフィルメント事業者とAPIで連携し、出荷作業の自動化を実現。注文が入ると外部倉庫へ自動的に出荷指示が送信され、ピッキング・梱包・発送までを一貫して外注化しました。
さらに『らくらくメルカリ便』など、ヤマト運輸などの物流パートナーとのシステム統合により、匿名配送・追跡機能・再配達削減も実現させています。
これにより人的リソースを削減しながらも、配送スピードと顧客満足度を大幅に向上させました。
メルカリは、外部物流とのシステム連携によってDXを成功させた代表的な事例として、多くのEC事業者の参考となっています。
中小・ベンチャー企業の物流DX化!成功事例 4選

中小やベンチャー企業の物流DX化の成功事例について4つご紹介いたします。
- ✓データ起点のD2C物流革新 | FABRIC TOKYO
- ✓人手不足に強い倉庫改革 | チュチュアンナ
- ✓AIで読み解く仕入れと出荷の最適化 | PALTAC
- ✓物流を持たない完全外部委託型モデル | BASE FOOD
データ起点のD2C物流革新 | FABRIC TOKYO
しかし、同社は顧客データをもとに受注生産型のビジネスモデルを構築し、外部のクラウド倉庫と連携。ピッキング・出荷・在庫管理をすべてアウトソーシング化しました。
これにより、物流拠点を自社で持たずにスモールスタートが可能となり、物流コストの最適化と迅速な商品発送を実現。
オーダーデータや生産ステータスもリアルタイムで管理され、サプライチェーン全体の可視化と自動化を可能とさせました。
データを活用した物流DXにより、顧客満足度の向上とブランド価値の強化に成功した事例です。
D2C物流の特徴など気になる方は、下記でも詳しく解説しているのでぜひこちらも確認してください。
人手不足に強い倉庫改革 | チュチュアンナ
特に繁忙期における人材確保と作業のバラツキが出荷遅延やミスの要因となっていました。
そこで同社は、外部の自動倉庫とWMS(倉庫管理システム)を連携させ、作業工程を大幅に標準化・省人化を実現。
バーコードスキャンによる誤出荷防止や、ピッキング効率を最大化するレイアウト最適化も実施しました。
その結果、作業時間を約30%短縮し、出荷ミスも大幅に削減。倉庫業務の外注化とDXの融合により、人手に依存しない強い物流体制を構築しました。
中小企業にとって現実的な、省人化×外部連携の成功事例です。
AIで読み解く仕入れと出荷の最適化 | PALTAC
そこでAIを活用した需要予測システムを導入し、仕入れ・在庫補充・出荷のタイミングを自動最適化。さらに、外部物流業者とのデータ連携により、入出荷のオペレーションの効率化を実現しました。
AIが各店舗の売上傾向や季節性をリアルタイムに分析し、最適な在庫数を算出。物流センターではこのデータに基づいて出荷が自動指示される仕組みが構築されました。
結果、在庫回転率が向上し、欠品率と保管コストを大幅に削減することを可能としました。
同社の取り組みは、AI活用と外部連携でサプライチェーン全体を強化するDXモデルとして注目を集めています。
物流を持たない完全外部委託型モデル | BASE FOOD
定期購入というビジネスモデル上、配送の遅延や在庫切れは顧客離れにつながる重大な課題でした。
そこで同社は、外部倉庫とシステム連携を行い、定期的な出荷処理を自動化。注文情報はAPIで倉庫側に即時連携され、梱包・発送・配送追跡までがワンストップで実行されます。
これにより、少人数でも高い物流品質を維持しながら、ビジネスのスケーラビリティを確保しました。
物流を内製化せずにDXを実現した好事例として、急成長スタートアップやD2C企業に大きな影響を与えています。
物流DXを行うための3つのポイント
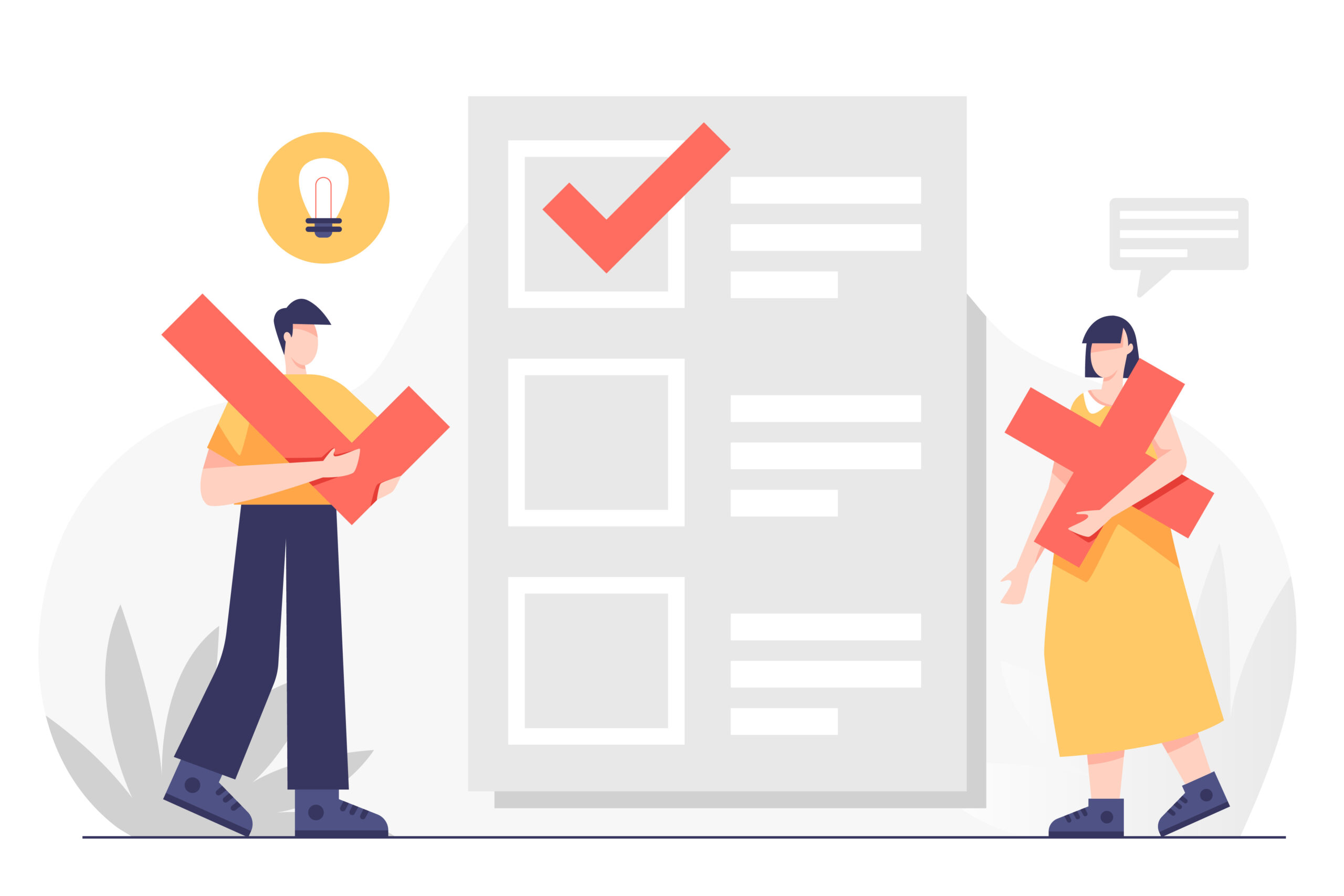
現場起点の課題設定と巻き込み
まずは『現場が何に困っているか』『どの作業にムリ・ムダ・ムラがあるのか』を丁寧にヒアリングすることが重要です。
トヨタ自動車でも現場、現物、現実の3つを徹底的に重視する『三現主義』という考え方が非常に重要視されています。
- 現場起点で進めるためのポイント
- ✓業務フローの可視化(棚卸、ピッキング、出荷など)
- ✓非効率の洗い出し(属人化・手作業・紙管理など)
- ✓スタッフの声を反映し業務上の“痛点”を明文化
- ✓小さな改善提案から始めてDX参加意識を醸成
また、現場スタッフを初期段階から巻き込むことで、『現場が使いやすいDX施策』になり、導入後の定着率も向上します。物流DXは現場の変革でもあるため、現場起点で考えることが非常に重要です。
段階的・小規模からの導入
そのため、まずは影響範囲の小さい業務や部署から部分的に着手する『スモールスタート』が推奨されます。
- 段階的導入の進め方例
- ✓在庫管理を紙からクラウドに移行 ※例:Googleスプレッドシート → WMS
- ✓ピッキングミス対策にバーコードスキャンを導入
- ✓特定エリアだけ業務自動化 ※例:出荷ラベル印刷の自動化
- ✓小規模拠点でテスト運用 → 成果を確認して他拠点に展開
このように、『試してから広げる』アプローチなら、初期投資も抑えられ、失敗のダメージも小さいです。
段階的に導入し、効果を見ながら徐々にシステム連携やアウトソーシング範囲を拡大していくことが、物流DXの成功確率を高める鍵となります。
物流パートナーやIT企業との連携強化
特に中小企業にとっては、外部の知見やリソースを活用することで、より効率的かつ確実にDXを進めることができます。
物流現場の業務改善には、ITベンダーや物流アウトソーサーとの連携が不可欠です。
- 連携強化で得られるメリット
- ✓WMSやTMSの導入・設定・教育をIT企業がサポート
- ✓外部倉庫とAPI連携し、受注〜出荷までを自動化
- ✓物流業務の外注化で自社はコア業務に集中可能
- ✓最新テクノロジー(AI・IoT・ロボティクスなど)を低コストで活用可能
また、外部パートナーと継続的に情報共有を行うことで、日々の改善提案や業務改善の提案も得られやすくなります。
『内製にこだわらず、連携で物流を進化させる』という視点が、今後の物流DX成功に欠かせない考え方です。
テルヰでは、物流DXを成功させるためにEC事業に特化した物流アウトソーシングサービス『HIGH LOGI』を提供しています。
高品質な物流サービスを提供するだけでなく、各お客様のニーズに合わせた物流提案を通して、物流最適化を図ることが可能です。
サービスについて詳細を知りたい方、無料見積・倉庫見学を行いたい方は、下記バナーよりお問い合わせできますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
物流DXを導入する5ステップ

物流DXを導入するためには以下の5ステップが重要です。
1
現状把握と課題の明確化
2
DX戦略・ロードマップの策定
3
ツール・システムの選定と導入
4
現場への展開と教育
5
効果測定と継続的改善
それぞれ順を追って解説していきます。
ステップ1:現状把握と課題の明確化
具体的には、入出庫や在庫管理、配送、返品処理など、物流プロセスごとの作業内容・コスト・リードタイム・人的リソースなどを洗い出し、業務ごとの効率や精度を数値で可視化します。
加えて、現場スタッフや管理者へのヒアリングを行い、日常業務で感じている非効率や課題を把握することも重要です。
例えば、『ピッキングミスが多い』『人手不足で繁忙期に対応できない』『在庫が合わない』といった現場の声は、DX導入のヒントになります。
こうしたデータと現場感覚を組み合わせて分析することで、優先的に解決すべき課題が明確になるでしょう。
このステップを丁寧に行うことで、後のステップでのDX施策の方向性が定まり、的確な対応策を検討するための基盤を築くことができます。
ステップ2:DX戦略・ロードマップの策定
まず、物流DXによって何を実現したいのかを定めましょう。例えば『誤出荷率を半減』『在庫管理精度を向上』『リードタイムを短縮』など、明確で測定可能な目標を立てることが重要です。
その上で、目的達成に向けた施策を段階的に整理し、短期・中期・長期で実行する計画を立てましょう。社内リソースの配分や必要な技術要件もこの段階で見極め、無理のない計画と体制を整えます。
また、DX推進には経営層の理解と支援も不可欠です。社内全体で共通認識を持ち、部門間の連携を図ることで、スムーズな実行につながります。
ステップ3:ツール・システムの選定と導入
業務内容に応じて、WMS(倉庫管理システム)、TMS(輸配送管理システム)、自動倉庫、RPAツール、可視化ダッシュボードなど、最適なテクノロジーを選びましょう。
なお、導入時は、自社の業務フローや既存のITインフラとの適合性、拡張性、運用のしやすさを総合的に検討することが重要です。
また、複数のベンダーを比較し、コストやサポート体制にも注意を払う必要があります。導入初期はトライアル運用を行い、現場からのフィードバックを得ながら必要な調整を加えていくことが重要です。
システムは入れるだけでは効果を発揮しないため、運用との一体化を意識した設計と展開が求められます。
ステップ4:現場への展開と教育
操作方法が理解されずに使いこなせなければ、せっかくのツールも機能しません。そのため、現場担当者に対する操作研修、マニュアル整備、業務フローの見直しなどを段階的に進めることが重要です。
特に新たなシステムに対する抵抗感や混乱を防ぐには、少人数での先行導入とフィードバックの反映が効果的となります。
また、現場スタッフの意見を尊重し、改善の余地がある部分は柔軟に対応する姿勢も大切です。
システムを『使わせる』ではなく、『使いたくなる』状態にすることで、現場の納得感を高め、DXが自発的に推進される環境を整えましょう。
ステップ5:効果測定と継続的改善
設定したKPIに対して、どれだけ目標を達成できているかを定期的に評価し、改善すべき点を洗い出しましょう。
例えば、出荷精度、在庫回転率、作業時間、配送遅延の件数など、実務に直結する指標を用いて、現場の変化を数値で捉えることが重要です。
データに基づいて改善策を講じることで、属人的な判断を避け、より効果的な運用が可能になります。
また、社内外のステークホルダーと定期的にレビューを行い、成功要因や課題を共有することも有効です。
こうした継続的な改善サイクル(PDCA)を根付かせることで、DXの効果が一時的なものではなく、企業の競争力として定着していきます。
物流DXを加速する公的支援と補助金の活用方法

国土交通省の物流DX支援策
特に注目すべきは中小物流事業者の労働生産性向上事業『物流施設におけるDX推進実証事業費補助金』です。
この補助金は、物流施設における自動化・機械化・デジタル化の取り組みに対して、システム構築や自動化機器の導入費用の一部の支援を受けることができます。
補助率は1/2以下で、システム構築・連携に対しては1社あたり最大2,000万円、自動化・機械化機器の導入には1社あたり最大3,000万円が上限です。
なお、申請にはシステム構築と機器導入を同時に行うことが条件となります。
申請期間や詳細な要件については、国土交通省の公式ウェブサイトをご確認ください。
参考:国土交通省ホームページ
活用できる補助金・助成金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)
中小企業者の生産性向上を支援する目的で、革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善に必要な設備やシステムへの投資を補助する制度です。物流業界でも、新しいシステムの導入や業務効率化を目的とした取り組みに活用されています。補助対象経費には、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費などが含まれます。
参考:ものづくり補助金総合サイト
物流効率化に向けた先進的な実証事業
この事業は、荷主企業の物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入等に係る費用を補助するもので、省力化や物流効率化の投資効果を明らかにする実証を行います。補助率は中小企業等で2/3以内、中堅企業等で1/2以内、補助上限額は中小企業等で1億円、中堅企業等で5億円です。
参考:持続可能な物流を支える物流効率化実証事業ホームページ
これらの補助金・助成金は、物流DXの導入における初期投資の負担を軽減し、プロジェクトの成功確率を高めるための有効な手段です。
申請にあたっては、各制度の要件や申請期間を確認し、適切な準備を行うことが重要となります。
また、専門家の支援を受けることで、申請手続きの円滑化や採択率の向上が期待できるでしょう。
物流アウトソーシング成功のポイント

物流DXを推し進めて行くには、自社リソースだけでなく、専門のアウトソーシング企業のリソースを活用することも重要になってきます。
アウトソーシングの活用は、単なる業務の効率化だけでなく、在庫管理の改善や配送ルート最適化、コスト削減など、DX化推進のためには不可欠な要素です。
次の項目にて、アウトソーシング成功の3つのポイントと、よくある失敗パターンと対策について解説していきます。
アウトソーシング成功の3つのポイント
- ✓①自社課題の明確化
- ✓②パートナー企業との情報共有・連携体制の構築
- ✓③柔軟な業務設計と継続的な見直し
①自社課題の明確化
成功の第一歩は、自社の物流業務で『何が課題なのか』『何を改善したいのか』を明確にすることです。例えば、在庫管理が煩雑でミスが多い場合は、倉庫管理システム(WMS)を備えた業者の導入が有効となります。
また、繁忙期の出荷対応が追いつかない場合には、柔軟に人員調整が可能な業者を選ぶことで対応力を高められるでしょう。
さらに、リードタイムが長くクレームが発生しているケースでは、発送スピードや立地条件を重視することで改善が期待できます。
このように課題を具体化することで、選定すべきパートナーや求めるサービス内容が明確になり、最適な業者選びに繋がるので意識するようにしましょう。
②パートナー企業との情報共有・連携体制の構築
アウトソーシングを成功させるには、委託先との綿密なコミュニケーションが欠かせません。具体的には、業務マニュアルや運用ルールを文書化して共有し、日次や週次で在庫数や出荷件数、誤出荷件数といったレポートの提出を依頼することが重要です。
また、定例会議を設けて現場の課題や改善提案を互いに出し合うことで、業務の透明性を高めることができます。
さらに、誤出荷率1%未満や当日出荷率95%以上といった具体的なKPIを設定し、委託先と『同じ目標』を共有することで、トラブルの早期発見や継続的な改善が促進されるでしょう。
③柔軟な業務設計と継続的な見直し
いきなり全ての業務を切り替えるのではなく、一部の業務から委託を始める『スモールスタート』をおすすめします。まずは『BtoC出荷業務のみ』を委託し、慣れてきた段階で『返品対応』や『在庫管理』なども徐々に拡張していく方法です。
さらに、月次で運用レビューを実施し、その都度改善点を反映させることで、業者との相性を見極めながら業務の安定性と効率を高めていくことができます。
このように柔軟に見直しや改善を重ねることで、長期的な信頼関係も築いていくことが可能です。
よくある失敗パターンと対策
失敗1:目的が曖昧なまま委託を開始
『コスト削減になればいい』など漠然とした理由で外部委託を進めると、業務フローや品質の不一致が発生しがちです。対策として、委託の目的・成果目標を数値で定め、関係者間で共有しましょう。
失敗2:丸投げによる品質劣化
業務をすべて委託し、フォロー体制がない場合、ミスや対応遅れが発生しやすくなります。対策として、定期的な進捗確認と品質チェック体制を構築しましょう。
失敗3:委託先との相性が悪い
価格や実績だけで選定し、業務理解や対応スピード、柔軟性が自社と合わないケースもあります。対策として、業務フローや担当者とのやり取りなど、トライアル導入で相性を確認してから本格導入を判断すると安心です。
選ばれる物流アウトソーシング企業の特徴

物流業務を委託する企業にとって、パートナー選びは事業の成否を左右する重要な判断です。選ばれ続ける物流アウトソーシング企業には、以下のような共通点があります。
- ✓対応力・柔軟性が高い
- ✓ ITシステムによる可視化と効率化が進んでいる
- ✓コストと品質のバランスが取れている
- ✓業種・業態に応じたノウハウを保有
選ばれる物流アウトソーシング企業とは、『単なる作業代行』ではなく、『物流のプロフェッショナル』として、クライアントと共に課題を解決し、ビジネスの成長を支える存在です。
委託を検討する際は、こうした特徴を持つ企業かどうかを見極めることが成功の第一歩となります。
テルヰの物流代行サービス『HIGH LOGI』が選ばれる理由
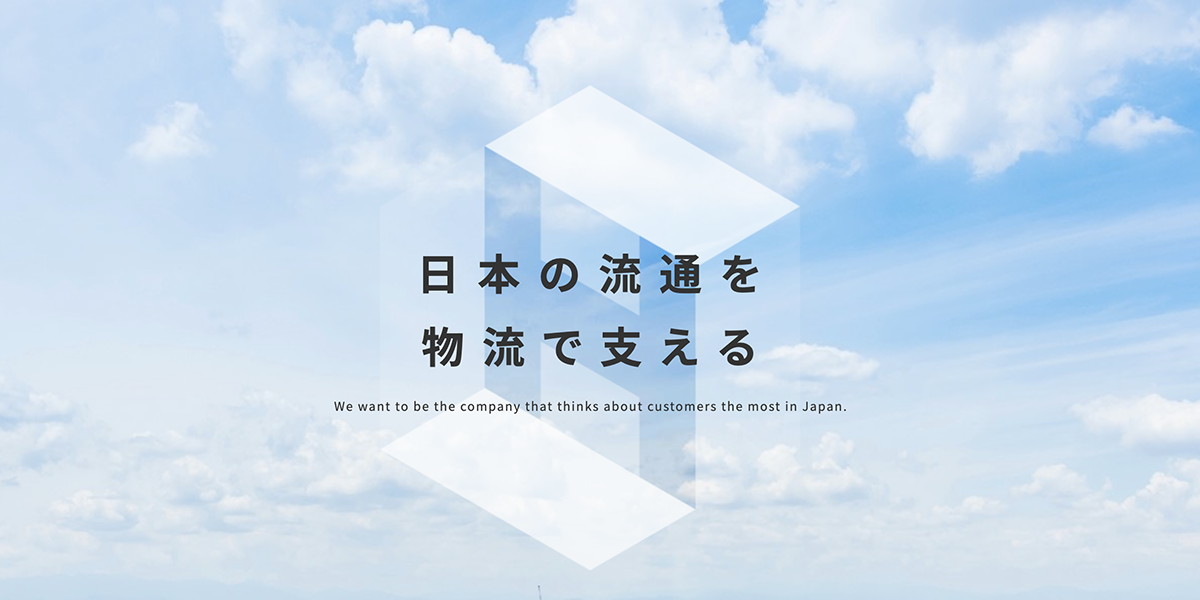
数ある物流アウトソーシング企業の中でも、テルヰの物流代行サービス『HIGH LOGI』が選ばれている理由は下記の4点です。
- ✓①柔軟な対応力と徹底した現場力
- ✓ ②見える化された高精度な在庫・出荷管理
- ✓③環境配慮・廃棄対応まで対応可能なワンストップ体制
- ✓④導入・運用サポートの手厚さ
まず、商品の特性や販売チャネルに応じて物流業務を最適化できる柔軟な設計力が強みです。また、WMSによる在庫・出荷の見える化と高精度な管理により、誤出荷や在庫差異を最小限に抑えます。
さらに、廃棄・リサイクル処理まで対応可能なワンストップ体制で、不要在庫の処分なども一括で委託可能です。これにより環境配慮とコスト最適化の両立が図れます。
加えて、導入支援から運用後の改善提案までサポートが手厚く、初めての物流アウトソーシングでも安心してスタート可能です。
多くの強みがある『HIGH LOGI』は単なる委託先ではなく、事業成長を支えるパートナーとして多くのお客様に評価されており、その信頼を裏切らないよう日々尽力しています。
もし、弊社サービスについて詳細を知りたい方や無料見積を取得したい方、倉庫見学をご希望の方は、下記バナーよりお気軽にお問い合わせください。
まとめ

物流DX導入のメリットと効果、7個の成功事例、導入するための5ステップについて解説してきました。重要なことは、自社に合ったDX化を段階的に推し進めていくことです。
いきなり、完全自動化を検討しても費用が合わなかったり、かえって手間になってしまったりするでしょう。一部をまず外部委託してDX化を推し進めることも一つの手段です。
もし、物流アウトソーシングを検討される際は、ぜひテルヰの『HIGH LOGI』をご検討ください。お客様に寄り添った高品質で迅速なサービスをお約束いたします。
関連記事
・個人でも始められる!EC事業の立ち上げ方と成功のステップ完全ガイド
・3PLについて知りたい!メリットや活用事例、おすすめ企業まで分かりやすく解説
・ECの成功事例7選!売上アップするための成功の秘訣をご紹介徹底解説










